2021年09月06日
色と栄養
じゅずつなぎコラム

愛知淑徳大学 教授 / 管理栄養士
東山幸恵
勤務先の大学では、座学だけでなく、実習も担当しています。その実習では、例えば病院などで提供する食事を想定して献立を立て、それを実際に調理する、といったことをやるわけですが、献立は、一定の栄養価の基準を満たすことはもちろん、「美味しく」「材料費を抑えつつ」「わかりやすい作り方で」「見た目に食欲がわくような」、などなどさまざまな要件が求められます。学生は頭をひねりひねり、献立を立てていきます。
特に、見た目は大きな難関。こってりした味噌味の煮物や、いかにもつややかな照り焼きなどは、まさにご飯の進む味である一方、全体的に茶色一色になると「映えない」印象が免れません。
美味しそうに見せるには、やはり「色」がポイントになるわけです。
では、どんな風に色を差し込むかというと、やり方は大きく2つ。1つは天盛り。煮物の上に木の芽を添えたり、小ねぎの刻んだものを散らしたりする方法です。2つ目は付け合わせ。料理のわきに色鮮やかなニンジンのマリネを添えたり、茹でたブロッコリーを添えることで、一気にお皿が鮮やかになります。
きっとお弁当などでも実感される方は多いのではないでしょうか。

「ベーコンとほうれん草の炒め物」
一番好きなほうれん草の食べ方
添えられた野菜の色に着目すると、濃い緑は「クロロフィル」、オレンジ色は「カロテノイド」という、光合成をおこなううえで欠かせない色素が元になっていて、栄養成分としても私たちの体にとってとても大切な働きをしてくれます。
こういった色の濃い野菜を「緑黄色野菜」ということがありますが、緑黄色野菜にはちゃんとした定義があるのをご存じですか?
「原則として可食部100g当たりにβカロテンが600μg以上含まれている野菜」、これが厚生労働省によって決められた緑黄色野菜の定義。太陽の光を浴びて作られた、鮮やかな色と栄養が緑黄色野菜の強みなんですね。

「ほうれん草の白和え」
実は、この定義に従うと、緑黄色野菜の代表であるようなピーマンやトマトは当てはまらなくなってしまいます。しかし、ピーマンやトマトのように、一般的によく食べられ、食べる量も比較的多く、カロテンも少なからず含まれている食品は、実質「緑黄色野菜」として扱われています。
ちなみに、現在100種類に近い野菜が緑黄色野菜として扱われており、ほとんどが緑や赤、橙色の鮮やかな野菜たちですが、一つ、意外な食材が入っているのです。早春に土手に生えている・・・そう、つくし。つくしは実はβカロテンが豊富な緑黄色野菜なんですよ。なお、βカロテンたっぷりのほうれん草が、オレンジ色ではなく緑色なのは、カロテンと同様に緑色のクロロフィルが豊富に含まれているから(肥料の影響もあります)。まるで絵の具を混ぜているようで、面白いですね。
- (0)
いいね!
<お願い>
・コメントはわっかスタッフの確認後に公開されます。営業時間外は翌営業日の公開になります。ご了承ください。
・個人情報の書き込みはご遠慮ください。
・投稿いただける内容は、著作権・肖像権など第三者の権利を一切侵害していないものに限ります。
・投稿されている内容を具体的に参考にする場合は、ご自身の責任においてお願いいたします。
コンテンツへのコメント
- 2021年9月 9日 22:22
- つぶらな瞳
天盛りと付け合わせは、若いころはできませんでしたが、年をとって食を楽しめるようになってから、しております。ゆっくり、味わっておいしく食べたいものですね。
- (0)
いいね!
- 返信
- 2021年9月 7日 09:42
- ぽぽりん
ほうれん草はついついサッと茹でてと思い込んでいます。ベーコンと炒めるほうが栄養価も高いですよね。同じメニューになりがちなので気を付けます。
- (0)
いいね!
- 返信
- 2021年9月 6日 18:41
- はな
子育て時代、生協製品でお弁当作り。茶色に薄いクリーム色のおかずであったの思い出しました。市販卵と違って卵黄も薄い黄色ですし。今はカップがカラフルなのがあって、ちょっとはごまかせますが、やはり我が家は基本茶色、健康色と思っています。
- (0)
いいね!
- 返信





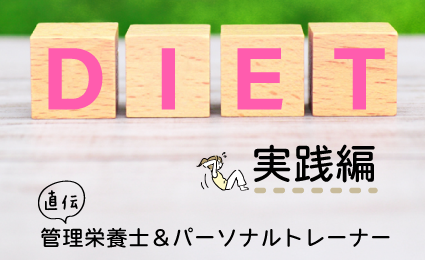

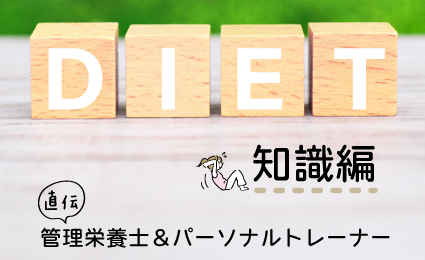

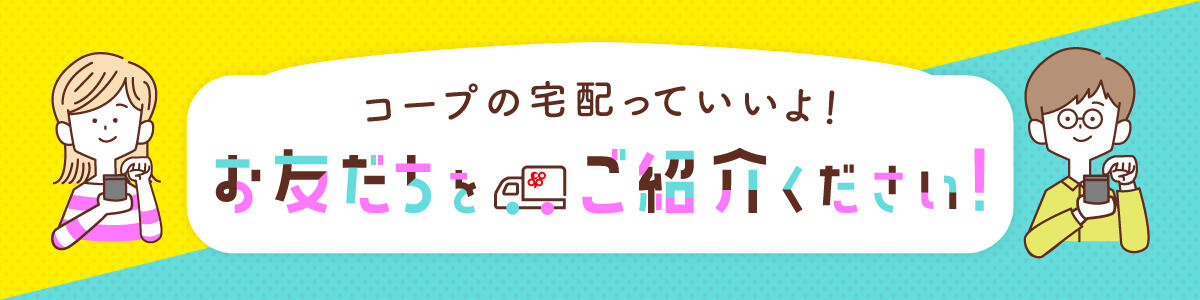
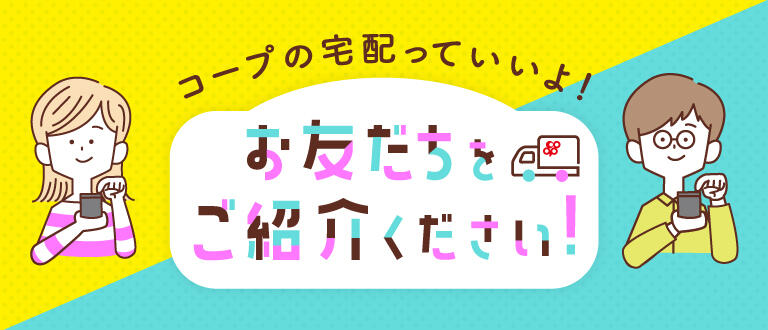
彩りは、気にして料理しておりますが、困ったときには、スリゴマが大活用。