2020年07月27日
お酢のチカラ (2)作り方を見学!
(初掲載「機関誌いずみ」2017年6月号より)
体が喜ぶチカラをもつお酢。今回も引き続きスマイルコープ「純米酢」でおなじみの(株)ミヅホさんに、純米酢の作り方を教えていただきました。
● 目次
● お酢の歴史
お酢はお酒を発酵して作られますが、日本ではいつごろから作られはじめたのでしょうか。
「諸説ありますが、日本では奈良時代に日本酒が造られはじめたとされ、お酢の起源もほとんど同じ頃だと考えられます。第二次世界大戦では、米が貴重だったため、石油を分解するなどの方法でお酢(合成酢)が造られていた時期もあります。昭和30年代中頃からは、お酒を発酵させて造る方法が復活しましたが、米不足のため、原料にコーンや小麦が用いられるようになりました」
お酢には長い歴史が、そしていろいろな材料や作り方があり、今では世界に4000種類もあると言われているそうです。
※合成酢...石油などを原料として化学合成で作られた氷酢酸を水でうすめ、化学調味料などで味をととのえたもの。
● お酢はどうやってできるの?
お酒を発酵させて作られるお酢ですが、実際どのようにしてできあがるのでしょうか。
ミヅホさんで米100%の純米酢づくりの様子を見せていただきました!
1. お酒を造る
まずは米から日本酒を造ります。米・麹・水・酵母を合わせて発酵させ、お酒の素であるもろみを造りますが、このとき米・麹・水を数回に分けて加えます。
もろみの造り方は、2回に分ける二段仕込みや、中には1回で仕込む会社もありますし、「初添え」「仲添え」「留添え」と本格的な三段仕込みなど、会社によって製法はさまざまです。(ミヅホさんは三段仕込み)

タンクの中をかき混ぜて、丁寧にもろみを仕込みます

アルコール度数は20度ほど
2. 発酵
次に、お酒とお酢、水を混ぜます。その中に酢酸菌を加えることで、1週間ほどで発酵が活発になり、3か月かけてお酒がお酢へと変わっていきます。

発酵温度を調整する木桶

表面から湯気が出ているのは、発酵している証
3. 熟成
発酵が終わると、熟成させて味を調整します。会社によって異なりますが、1〜3か月ほど寝かせます。長期間寝かせるほど、味がまろやかになります。

吉野杉で作られた伝統的な桶で発酵・熟成します
4. ろ過・殺菌
できあがったお酢をろ過して、熱殺菌を行います。そのままびん詰めして完成です。
● 三択クイズで酢!
お酢の性質として、正しいものはどれでしょうか?
① 酸性
② 中性
③ アルカリ性
お酢には殺菌力がありますが、次のうち効果のないものはどれでしょうか?
① 大腸菌O-157
② カンピロバクター
③ ノロウイルス
お酢は掃除にも使えますが、効果的なものは次のうちどれでしょうか?
① お風呂の皮脂汚れ
② 洗面台のせっけんカス
③ 洗濯機のカビ
① 酸性(酢酸が主成分のため)
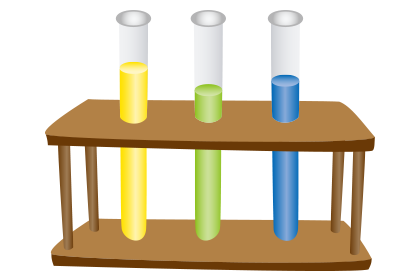
③ ノロウイルス(塩素系の消毒剤でなければ効果がないため)
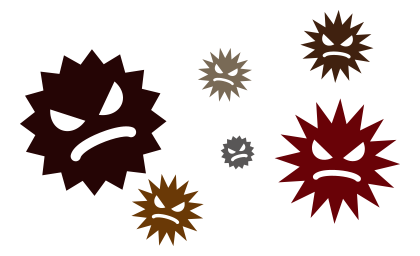
② 洗面台のせっけんカス(せっけんカスはアルカリ性のため、酸性の酢が有効。皮脂汚れやカビは酸性のため、アルカリ性の洗剤が効果的)

お酢がお酒からできることはなんとなく知っていても、そのお酒を造る所から始まると聞くと、あらためてお酢は時間と手間をかけて作られるんだなぁと実感します。
第3話は、お酢を使ったレシピをご紹介します!

 純米酢
純米酢
今回お話をうかがったミヅホ株式会社では、お酢の素である日本酒にこだわり、造り酒屋と同じ手間暇をかけた「三段仕込み製法」で日本酒を造っています。奈良の吉野杉でできた木桶で、3か月以上じっくりと発酵・熟成させることで、芳醇でまろやかな味わいに仕上げています。
- (0)
いいね!
<お願い>
・コメントはわっかスタッフの確認後に公開されます。営業時間外は翌営業日の公開になります。ご了承ください。
・個人情報の書き込みはご遠慮ください。
・投稿いただける内容は、著作権・肖像権など第三者の権利を一切侵害していないものに限ります。
・投稿されている内容を具体的に参考にする場合は、ご自身の責任においてお願いいたします。

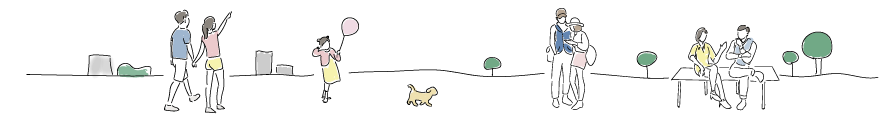
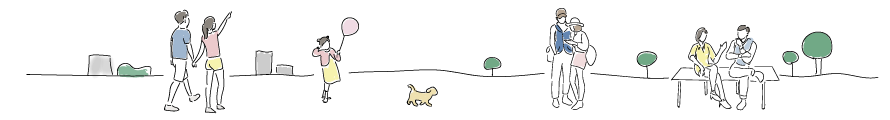






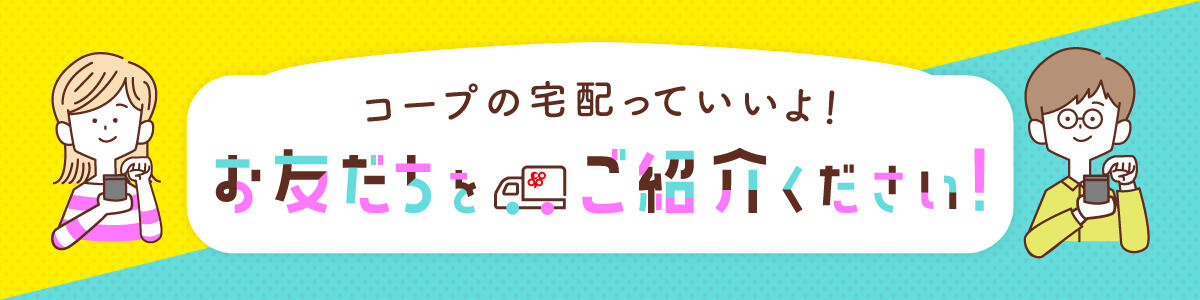
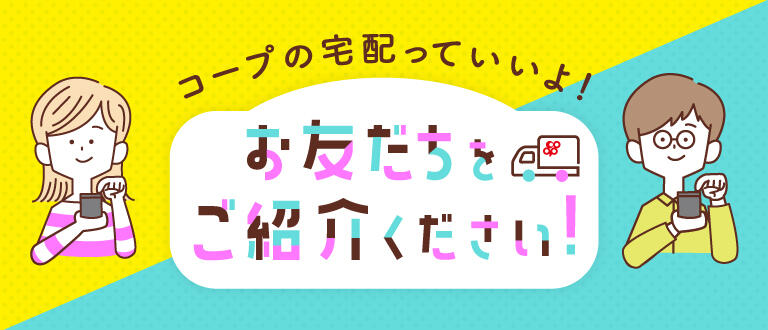
生姜・紫玉ねぎ・パプリカ・焼いた舞茸の4種は、各4本の便に、純米酢だけで漬けてあり、舞茸は血糖対策に。しょうがは現在新新生姜なので、カツオのタタキや焼き魚に千切りに切ってかなり多く、紫玉ねぎ・パプリカはサラダのトッピングに、また生で保存するより日持ちして、重宝しています。